ブレーキ雑学講座
電車のブレーキ その7 ブレーキ操作と止まり方
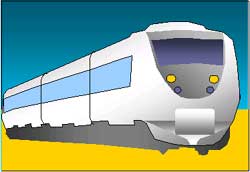
次はJR在来線、私鉄です。
一般的にはATS(Automatic Train Stop,自動列車停止装置)が使われています。
いわば新幹線ATCの簡易版です。ブレーキ操作はやはりブレーキハンドルで行います。
乗車率、立ち席乗客、車間間隔、運転間隔など新幹線より厳しい条件もあるため、
高度の熟練が要求されます。
新幹線と同じように高速時は回生ブレーキまたは発電ブレーキ(回生電気を使えないローカル線)
で、低速からは機械式ブレーキで止まります。
(最近では、停止まですべて電気ブレーキの車両が
一部実用化されているとのことです。高度な制御技術のたまものです。)
なお、JR在来線、私鉄は法律で停止距離600m以下と定められているため、実用上
(新幹線は専用線路で踏み切りがないため規制はありません)、最高速度は時速130km位が限界です。
この結果、残念ながら在来線では、一部の区間を除き、20年間近く最高速度のアップはありません。
最後はモノレール、新交通です。
これらの車両は、タイヤで走行していますので、理論的には電車より大きな減速度を得ることができます。
しかし乗客の安全、快適性を考え電車並みの減速度としています。
ブレーキハンドルの操作方法は新幹線、JR在来線、私鉄とほぼ同じです。高速からは電制回生ブレーキ、
低速からは機械式ブレーキで止まります。
最近は無人運転で運行されている車両もあります。これはコンピュータが地上設備、電車の
両方から電車位置、走行速度、車重、前後の電車状況などの情報を取り込み、ブレーキ力(ノッチ位置)
、作動タイミングなどを計算し、自動的にブレーキをかけることができるシステムです。
全般の制御という点では、新幹線のATCに似ていますね。
停止位置の誤差は数10センチ以内だそうです。(余談ですが、このような車両に使われている
パッドでは摩擦性能の精度が非常に厳しいと関係者一同ぼやいています。)
最近では、新交通に限らず、安全性向上のため地下鉄、在来線でもホームドアが増えて来ました。
運転手の技に頼らず、ピタリと止める技術の進歩はどこまでも要求されることでしょう。

ホームドア


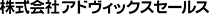
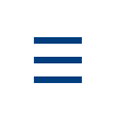

 品番検索
品番検索 FAQ
FAQ