ブレーキ雑学講座
「鳴き」の話 その1 発生のメカニズム
発生のメカニズム
パッド開発テーマでは、「効き」と「鳴き」が両横綱です。特にブレーキメーカーで
はこの「鳴き」が、開発担当者の「泣き」に結びついているのは、冗談と本音が半分ずつです。
これから、2回に分けて、この「鳴き」についてお話しましょう。
また、「メンテナンス」のコーナーに、「鳴き」の具体的対策の説明がありますので、そちらもご参照下さい。
-◎--◎-
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
ブレ-キの最も重要な性能は車を止めることだが、それ以外の性能ももちろん要求される。車が高級化しどんどん静かになってきたのに伴い、特に問題になってきたのが制動時に生じるブレ-キの騒音。ブレ-キをかけたときに「ピ-」とか「キ-」とか出る、あの音のことである。
これを専門的にはブレ-キの「鳴き」という。もっと低い音で、体に伝わる振動レベルのものは「異音」といい、これはまた別の機会にお話する。
ブレ-キが鳴いたからといって、効きやパッド減りが悪くなるというものではなく、純粋に「気持ち・格好良さ」だけの問題である。そんなの構わないではないか、と言って下さるお客様は神様で、実際に気にされる方はとても多いのである。そんなわけでブレ-キの開発には、鳴きの対策が大きな割合を占めている。
モノとモノがこすれ合えば、当然音が出る。それを良い方に使っているのが古くは蓄音機・レコ-ドプレ-ヤ-、そして優雅なバイオリンもしかりである。音を出したくないのに出てしまってヒンシュクを買っているのが、ブレ-キの鳴きとタイヤのスキ-ル音(タイヤの限界近いところでキュルキュルとかキ-という、あの音)である。とはいっても、タイヤの音は快感、と感じる方も居られるようだが。
それでは、鳴きを少なくするのにはどうしたらよいか。鳴きの発生メカニズムから考えて見よう。これはブレ-キと、バイオリンを対応させると分かり易い。

鳴きの発生源はパッドとロ-タの擦れる面で、ここが振動することから始まる。バイオリンでは、弦と弓の擦れるところに対応する。ところが振動するだけでは、大きな音にはならない。これを効率よく音に変えるモノが必要である。小学校の理科の授業で習った、「音叉」という鉄製のU字型のものを覚えて居られるだろうか。この音叉をいくら強く叩いて振動させても、それだけでは小さな音しか出ない。ところが音叉を「共鳴箱」というがらんどうの箱に乗せるとあら不思議、急に大きな音が出るのである。ブレ-キでこの「共鳴箱」に対応するのが、おもにディスクロ-タである。まず振動して、さらに音を大きくするという、一人二役の活躍なのである。ちなみにバイオリンでは、共鳴箱は木で出来た胴体に対応する。
このように「鳴き」は振動を起こす部分と、その振動を音に変える部分とがあって、初めて発生するのである。
・・つづく。


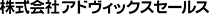
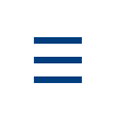

 品番検索
品番検索 FAQ
FAQ