ブレーキ雑学講座
「鳴き」の話 その2 対策の考え方
対策の考え方
前号で、発生のメカニズムはおおよそ分っていただけたかと思います。今回は、対策の基本的な考え方についてのお話です。
-◎--◎-
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
それでは鳴きを止めるには、どうしたらよいのか。
まずは、振動を出さない方法。一番簡単なのは、擦れたときの引っかかりをなくすことである。例えばバイオリンでは、あらかじめ弓(馬のしっぽの毛を束ねたもの)に、ネッチャとした「松ヤニ」を塗り付けている。こうして弓と弦との引っかかり、即ち摩擦力を大きくしている。この「松ヤニ」の代わりに、すべすべの「ロウ」などを塗れば、もうこれは弦を擦ってもスカスカで、音などしない。
ところがもうお分かりのように、この方法はブレ-キには無闇に使えない。鳴きは止まったが、車は止まらなかった、と本末転倒の笑えない状態になるのである。
とはいえ、ブレ-キの鳴きが出やすいのは、何かの加減で急に摩擦力が高くなるところである。そこでパッドの開発では、突発的に異常に高い摩擦力が出ないような設計をしている。実際は非常に軽いブレ-キの時に摩擦力が高くなる場合が多いので、ここを改良する。この改良だと強くブレ-キを掛けたとき、すなわち効いて欲しいときにはしっかり効くので問題ない。
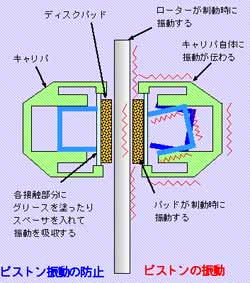
2番目の方法は、振動を止める方法である。
バイオリンなら(ギタ-も)振動している弦を、指か何かでつまんでやれば良い。
実際に弱音器という、弦にはさんで音を小さくする器具がある。
ブレ-キではどうするかというと、ブレ-キング
の際、パッドとロ-タをしっかり密着させることである。何事もそうなの
だが、不安定な状態だとカタカタとぶれが生じて振動が止まらないので、これを
なくすと良い。
具体的にはパッドを柔らかくして面当たりを良くしたり、振動を
吸収しやすいような材料に設計している。またキャリパ-を振動しにくい設計に
したり、ピストン位置・個数の変更、キャリパ-とパッドの固定法を改良し対応
している。
最後の方法は振動を音に変えにくくする、つまり音を響かせない方法である。
バイオリンの場合には胴体(共鳴箱)を取ってやればよい。ミュ-トバイオリンという、胴体が枠だけのちょっと情けない形のバイオリンがあるが、これはほとんど音がしない。同様にエレキギタ-もアンプやスピ-カにつながなければ、びっくりするほど小さな音しかしない。これもエレキギタ-の胴体は「板」であって、アコースティックギタ-の胴体のような「共鳴箱」ではないからである。ブレ-キの場合には共鳴箱のロ-タを取るわけにはいかないので、ロ-タに響きにくい材質を用いたり、形状を工夫して対応している。
具体的な対策は、整備編を参照下さい。


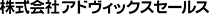
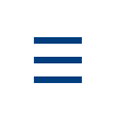

 品番検索
品番検索 FAQ
FAQ