ブレーキ雑学講座
電車のブレーキ その2 ブレーキの種類
ブレーキの種類
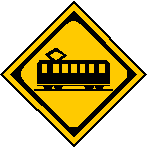 今回はブレーキの種類です。
今回はブレーキの種類です。
まず初めに、分類してみましょう。
クルマと比較して、随分、いろんなブレーキがあるとお思われるでしょう。
勿論、ひとつの電車にこれだけ全てついている訳ではありません。
2~3種類の組合わせでついています。
| 電気式ブレーキ | 発電ブレーキ |
| 回生ブレーキ | |
| 渦電流ブレーキ |
| 機械式ブレーキ | 踏面ブレーキ | |
| ディスクブレーキ | テコリンク式 | |
| 油圧キャリパー式 | ||
| レールブレーキ | ||
まず電車のブレーキは、非接触の電気式ブレーキと、
ディスクブレーキの様に摩擦力で止める機械式ブレーキとに大別されます。
電気ブレーキには、従来よりある発電ブレーキと最近の主流である回生ブレーキがあります。
機械式ブレーキは、基礎ブレーキともいい、読んで字のごとく一番ベースとなるもので
電気ブレーキが失陥した場合、この基礎ブレーキだけで止る必要があります。
詳細は、次回以降にご説明します。
今回は、この電気式ブレーキと機械式ブレーキの使い分けです。
まず、電車にはモーターのついているM車(電動車)とモーターのないT車
(トレーラー車)があり、ひとつの編成は、M車とT車が一定の比率で組合
わされています。
M車では、主に中・高速域では電気式ブレーキを、低速域では、機械式ブレーキ
に切り替ります。勿論、T車は、電気式ブレーキがないので、最初から機械式ブレーキだけで止ります。
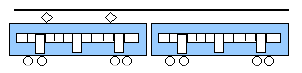 最近では、集電性能が向上したので、M車でもパンタグラフがついてないケースが
多いようです。
最近では、集電性能が向上したので、M車でもパンタグラフがついてないケースが
多いようです。
具体的には、新幹線の場合、回生ブレーキとディスクブレーキの組合わせが 一般的で、中高速では回生ブレーキでのみ減速し、ディスクブレーキが かかるのは、ホームに止まる寸前(時速30km未満)くらいです。 ホームに入ってきて、モーター音が止り、惰行運転に入った後、ようやく 機械式ブレーキの出番となる訳です。
実際の制動力負担ですが、通常のレベルでは、全体のブレーキ量の内、
回生ブレーキが95%以上で、残りのわずか5%程度が、ディスクブレーキと言われています。
ちなみにフランスのTGVは大半がT車を機関車で牽引する方式なので、この
比率は新幹線と逆転し、3:7程度とのことです。
在来線の場合は、回生ブレーキ(従来は発電ブレーキ)とM車は踏面ブレーキ、T車はディスクブレーキ
の組合わせが主流です。T車の比率が多いので、負担比率は、半々くらいでしょうか
尚、最近の電車では、「遅れ込め制御」という制御技術を
用いて、T車が負担するブレーキ力もM車の回生ブレーキで出来るだけカバーし、
機械式ブレーキ作動を抑え(=パッド摩耗を抑え)ようとしているのが一般的です。
「ウーン、パッドがなかなか減らないなあ」とは、パッド製造メーカーのつぶやきです。


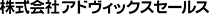
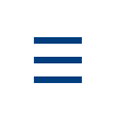

 品番検索
品番検索 FAQ
FAQ