ブレーキ雑学講座
電車のブレーキ その3 電気式ブレーキ
電気ブレーキ
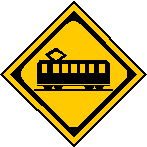 今回は、電気式ブレーキの話です。
今回は、電気式ブレーキの話です。
| 電気式ブレーキ | 発電ブレーキ |
| 回生ブレーキ | |
| 渦電流ブレーキ |
電気ブレーキには、大きく分けて、従来からある発電ブレーキと比較的新しい電力回生ブレーキ
(以降回生ブレーキと略)のふたつがあります。
発電ブレーキとは、走行時に使うモーターを用いて、これを抵抗器にして制動エネルギーを
熱エネルギーに変換しブレーキとする訳です。昭和30年代に登場した在来特急「こだま」に
使用されていて、既に40年くらいの実績があります。
これに対し、回生ブレーキとは、1980年代の終わり頃から登場した新しい方式で
ブレーキをかけて発生する電気を電線に返して(回生)やるという省エネ時代に
ぴったりです。電圧の高いところから電圧の低いところに電気は流れるという理科
の時間に習った原理そのもので省エネ時代にピッタリですね。
駅間距離がせいぜい1Km程度で、加減速を繰返し、かつ電車密度が高い地下鉄にはぴったりです。
走行中の電車が多いから、常に電圧は低めの状態になっている訳です。
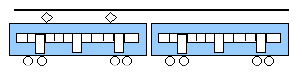 電車の回生発電能力がいくら高くても、電線の電圧レベルが低くないと
役目を果せません。
電車の回生発電能力がいくら高くても、電線の電圧レベルが低くないと
役目を果せません。
この方式はなんと高速エレベータにも採用されており、降下時に電力回生させているそうです。
似たような例ですが、
クルマに詳しい読者のみなさんは、トヨタのプリウスが、ブレーキ時のエネルギーでバッテリー
を充電しているのは、よくご存じですね。
しかし、残念ながらこの回生ブレーキにも欠点はあります。先ほどの原理と逆で、
返す電線(き電線といいます)側の電圧が高いときは、電気を返せなくなる(回生失効)ことがあるのです。
このときは、機械式ブレーキの出番となります。
最近では、この欠点を補うため、回生ブレーキと発電ブレーキを両方積んだ二刀流の電車も
登場しています。田舎に行くと、電車密度が低く電力負荷が小さく、回生ブレーキの効果が
小さくなってしまいます。このときは発電ブレーキに切り替える訳です。
如何にも日本的な芸の細かさですね。
業界表現では、「発電・回生ブレーキ併用・・・」という表現になります。
 うず電流ブレーキは、名称からは想像がつきにくいブレーキですが、ひとこと
で言えば、電磁石でローターを止める電磁ブレーキの一種です。新幹線の
100系、300系(のぞみ)のT車についています。
うず電流ブレーキは、名称からは想像がつきにくいブレーキですが、ひとこと
で言えば、電磁石でローターを止める電磁ブレーキの一種です。新幹線の
100系、300系(のぞみ)のT車についています。
ディスクを挟んでいる様は、巨大なディスクブレーキみたいですネ。
次回は、機械式ブレーキの話です。


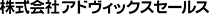
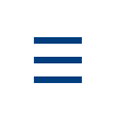

 品番検索
品番検索 FAQ
FAQ