ブレーキ雑学講座
電車のブレーキ その5 特殊なブレーキ
特殊なブレーキ
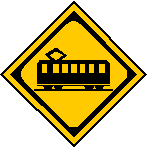 電車シリーズ最終回は、特殊なブレーキの話です。
電車シリーズ最終回は、特殊なブレーキの話です。
レールブレーキ
機械式としては、レールに直接摩擦材を当てて、止る方式です。 電気式としては、電磁石をレールに近づけ、渦電流で止める方式です。 正式には、電磁吸着式レールブレーキといい、寒冷地等で試験的に 使われました。
レールが痛むのでメンテナンスが大変なため、今では使用例をあまり 聞きません。
空力(くうりき)ブレーキ
時速500kmともなると電気式、機械式ブレーキのみでは停止距離が 長くなってしまいます。そこで第3のブレーキとして登場したのが 空力ブレーキです。飛行機が、着陸する際、フラップを下げる原理と同じ です。電車では、未だ実用化していませんが、リニア新幹線で開発中 です。
中国のように広いところを走るのならば、巨大パラシュートでも 使えないのかと素人考えもあります。!(^^)!
→ JR総研さんのHP
耐雪(たいせつ)ブレーキ
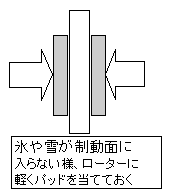 北国を走る電車は常に氷と雪に襲われる危険性があります。ブレーキ パッドとディスクのと間が氷りついてしまうと全くブレーキの役目を果しません。 耐雪ブレーキは軽くディスクローターを挟んでおき この氷が入り込まない様にするブレーキ作動のことです。
北国を走る電車は常に氷と雪に襲われる危険性があります。ブレーキ パッドとディスクのと間が氷りついてしまうと全くブレーキの役目を果しません。 耐雪ブレーキは軽くディスクローターを挟んでおき この氷が入り込まない様にするブレーキ作動のことです。
抑速(よくそく)ブレーキ
下り勾配の長い坂道では、速度を抑える必要があります。そのため エンジンブレーキ(モーターを制御)をかけたり、機械式ブレーキ をかけたりします。これらを抑速ブレーキといいます。山の多い日本では このような使われ方も多いんです。
最後のテーマは、
「電車は、どれくらいの距離で止ることが出来るのか」です。
非常ブレーキは、最大のブレーキ力を出すため、電気式ブレーキと機械式を 同時に作動させます。もっとも鉄道の場合、レールと車輪の摩擦力(粘着力) が圧倒的に小さいためクルマと同じように短距離での停止は困難です。
例えば、新幹線 等で地震等が発生し緊急停止が必要な場合、時速300kmからでは、停止迄 に4km程度かかります。クルマの場合なら、800mくらいでしょうか。 また在来線の場合は、法律で600m以内で停止出来ることが義務づけられて いるため、最高時速は130km迄となっています。今の技術なら、走るだけなら 在来線でも時速180kmも簡単でしょうが、この600mの制限をクリヤするのは 大変です。
最高時速120kmの特急電車が世に出て、既に40年以上たって いるのに、いまだ在来線の最高速度が130kmであることをご存じですか? 踏切があることや、曲線が多いため視野が狭いことが在来線の制約条件でしょう。
尚、最近の新幹線では、ABS(滑走制御装置といいます)は勿論のこと、 レールとの粘着力を高めるためセラミックの粒子を吹きかけたり、車輪踏面を 磨いたりと、皆さんの知らないところで種々の苦労をしています。


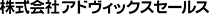
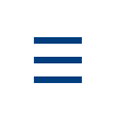

 品番検索
品番検索 FAQ
FAQ