ブレーキ雑学講座
山道でのブレーキング雨の中のブレーキング
ドライブに最適なシーズンが到来しましたね。今回は山道でのブレーキングです。
山道、特に下り坂での運転は注意が肝心です。万が一、ブレーキが効かなくなったら谷底へ転落!なんてこともあります。下り坂では、「エンジンブレーキをかけながら、ブレーキングは最小限に」が常識です。では、下り坂では、ブレーキはどのようになって
いるのでしょうか。
曲がりくねった坂道では、どうしても頻繁にブレーキングしなくてはなりません。
その結果、ローター及びパッドの温度が高くなってしまいます。
通常の街乗りでは、ローター温度は100~150℃くらいですが、坂道では300℃、場合により500℃以上になることがあります。
しかも、長い坂道では、このような温度に長時間さらされることになります。
すると、有機物でできているパッドは、その表面が熱分解して、ガスが発生するため、効きが著しく低下します。
いわゆる、フェード現象(雑学講座1参照)です。前兆として、有機物(レジン)の焼ける臭いがします。このような時は、直ちに停車し、ローター、パッドを30分程度冷やすことをお勧めします。
また、長い下り坂を常時ブレーキをかけながら、ユックリ降りてきますと、ブレーキ液が沸騰してブレーキが効かなくなるベーパーロック(雑学講座2参照)がおきることもあります。
速度が低いため、風による冷却が不十分となり、ローターで発生する熱が、パッド、キャリパを通してブレーキ液に伝わり、ブレーキ液温が沸点以上(約230℃以上)になるためです。
このような時も、あせらず直ちにパーキングブレーキで停車し、そのまま車を放置して冷やすことをお勧めします。
なお、曲がりくねった登坂で長時間走行した後の最初のブレーキングでペダルが伸びることがたまにあります。ノックバックと言い、キャリパブレーキのピストンが走行中にローターで叩かれて、パッドとローターのクリアランスが大きくなるためです。
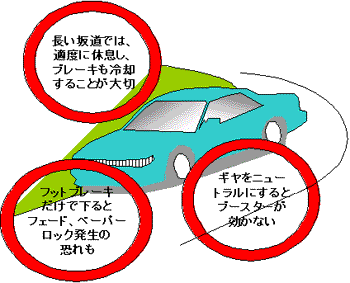
下り坂では、「エンジンブレーキを使って、スピードは控えめに、ブレーキは控えめに」運転してください。なおエンジンを切ったままとか、ニュートラルギヤでブレーキのみで降りることは絶対しないでください。真空倍力装置(エンジンが切ったままでは非作動)が効かなくなり、ブレーキの効きが著しく低下します。
なお、坂道等でハードなブレーキングした場合は、パッド表面の劣化(色、状態などでわかる)、偏摩耗(片減り)などが生じますので、パッド表面を研磨すると良いでしょう。またローター表面の付着物(効き低下、鳴きの原因となる)を落とすため、ペーパー研磨するのも良いでしょう。
坂道を頻繁に降りられる方は、耐フェード性のあるスポーツパッドの使用、ブレーキ液のグレードアップ、アルミホイールへの変更(冷却性能アップ)への変更などが効果あります。


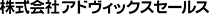
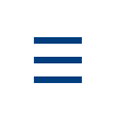

 品番検索
品番検索 FAQ
FAQ