ブレーキ雑学講座
パッド製造のあらまし
連載が続いたので、これからしばらく、単発のもので講座を続けましょう。
パッドの作り方を教えて欲しいとのお便りをよくいただきますので、 今回は、大まかな製造工程について、ご説明しましょう。

まず、一番左上の部分をご覧ください。
まず、10数種類の原料粉を秤量し、
ミキサーで混合するところから始ります。この原料の配合で、パッドの性能の殆ど
が決定される重要な工程です。(この混合粉が、いわゆるパッド材質のことで、
大まかな分類については、雑学講座の10をご覧ください)
次に、予備成形という工程でこの混合粉を、後にくる成形時に粉がこぼれない様
に、ビスケット状に軽く押し固めておきます。
一方、バッキングプレート(いわゆる裏板)では、油分を取除いた後、接着材を薄く塗布します。 次の成形工程では、バッキングプレートをセットした上に、金型にビスケット状の混合粉を入れ、 百数十℃で加熱成形を行います。ここで、パッドの形となります。

次の硬化工程では、パッドを200℃以上で長時間かけて、じわりじわりと焼上げます。この工程 でパッドの性能の安定化と機械的な強度が確保されます。 (陶器の窯入れに似ています)
この後、塗装し、焼付・乾燥、パッド面の研磨や溝入れ、面取り等の一連の加工
が続きます。
最後のスコーチという工程ですが、これは表面を軽くこがしてやり、いわゆる「焼入」
状態に仕上げます。乗用車用では、この焼入処理は過半数のパッドに行っています。
すなわち最初からよく効くパッドになっているのです。
この後、製品検査を終えて、ようやく完成です。
以上の説明で、おおよその流れを理解いただけたと思います。
どうです。見かけと違って、作るのが大変なことがわかっていただけたでしょうか。
更に、このあとお店に並ぶまでには、箱詰作業やラベル貼り等延々と作業が続きます。
何?設備やら製品の写真が全然ない、もう少し具体的に教えて欲しい? 残念ながら、パッドの工程は、
それが出来ないんです。理由? 言えません。具体的な作り方は秘密なんですヨ。
・・・・・ということで、また次回。 <(_ _)>


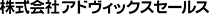
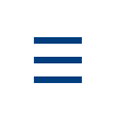

 品番検索
品番検索 FAQ
FAQ